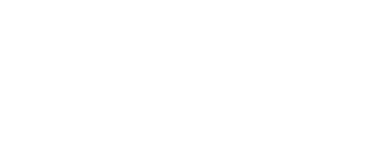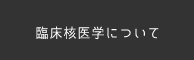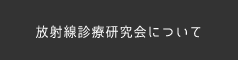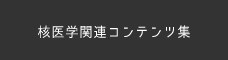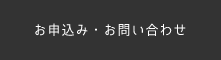放射線診療研究会は1966年に創設された伝統のある研究会で、主として関東地方において核医学に従事する医師、診療放射線技師、基礎系の研究者、関連する企業の関係者などの集まりです。研究会ではワークインプログレス、技術講演、一般演題、特別講演などの発表があり、毎回の出席者は40~60名程度でアットホームな雰囲気のなかで行われるため、気がねなく演者に質問し、議論を深めることができます。症例検討会が行われることもあり、出題者が症例を提示し、質問に参加者が答える方式で進められます。食事をとりながらメンバーの親睦を深め、情報の交換を行う情報交換会が催されることもあります。2020年のコロナ禍以降は、研究会はweb開催でおこなわれることが多くなりましたが、職場や家庭での参加も可能となり、便利さの面からは好評のようです。日本核医学会の核医学専門医制度において、学術集会の参加単位(単位数3)が認められております。
本会のもうひとつの特徴に機関誌である「臨床核医学」の発行があります。本研究会や他の学会、論文などで発表された研究のなかから興味深いものを選定し、発表された先生に概要の執筆をお願いしており、注目の話題に触れることができます。またいくつかの連載記事が企画されており、医師や研究者が核医学の基本的な知識を身につける、あるいは知識を整理するのに役立つように配慮されています。放射線診療研究会のホームページでは、過去の臨床核医学のすぐれた記事を参照することができ、臨床核医学誌以外の教育的なコンテンツも充実しています。
2016年に放射線診療研究会は50年目を迎え、次の半世紀を歩み始めています。最近は核医学をとりまく状況も変化し、ここ数年でルタテラ、ライアットといったRI内用療法が保険診療で可能となり、今後もtheranosticsの概念に基づく新しい核医学治療の登場が予想されています。これまでFDGのみであったデリバリで供給されるPET製剤の種類も増え、脳腫瘍の病巣の範囲を評価することのできるフルシクロビン、認知症の背景病理にせまるアミロイドイメージング剤も上市されました。さらに画質と定量性に優れた18F標識のPET用心筋血流製剤の登場も期待されます。発展を続ける核医学診療の変化を鋭敏に映し出す鏡として、未来の核医学の方向性を照らし出すガイドライトとして、診療研究会から発信する情報が核医学に従事される方々の活動の一助になればと願っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2025年1月
放射線診療研究会会長
橋本 順

放射線診療研究会会長
橋本 順
東海大学医学部専門診療学系画像診断学